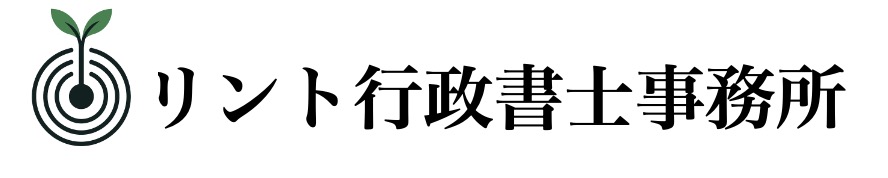本気で融資を受けるための「創業計画書」
いつもご覧いただきありがとうございます。行政書士の林です。
創業時は、設備投資などの出費がかさみ、経営が苦しい場合が多くなります。
設備資金や運転資金を自己資金だけで賄っても構いませんが、手元のキャッシュのことを考えると、融資が非常に重要な資金調達の手法です。創業融資の活用については以下をご覧ください。
ただ、創業時は過去の実績がないため、融資申込時点での状況や将来の見込みを基に融資の可否が審査されます。
その審査において最も重要な資料が創業計画書です。
今回は、創業計画書について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
創業計画書とは
創業計画書は、融資を受ける際、金融機関等に自社の将来像を共有してもらうための書類です。
代表的なものとして、日本政策金融公庫の創業計画書を例に進めます。
(参考 日本政策金融公庫 各種書式ダウンロード)
創業計画書には、大きく分けて定性面と定量面の2種類について記載します。
定性面・・・創業の動機、創業者の経歴、取扱商品・サービス、セールスポイント、顧客ターゲットなど
定量面・・・資金計画(借入状況、資金使途など)、収支計画(事業の見通しなど)
創業時には過去の実績がないため、創業融資では定性面が重視されます。
例えば、創業者の経歴として「創業しようとしている業界の経験があるか」や、通帳を確認して「資金管理を適正にできるか」などが重要とされています。
また、創業への決意や続ける覚悟、家族の理解も大切なポイントです。初めから事業が軌道に乗ればよいですが、なかなかそうはいきません。そんなときに家族が応援してくれなかったり罵声をあびせられたりすると、いくら本人のやる気があってもどこかで気持ちが折れてしまうことが多かったりするのです。
では定量面に関しては適当に書いてもいいかというと、もちろんそうではありません。
特に収支計画については売上の根拠をできるだけ具体的に示し、そのうえで返済財源を明確にする必要があります。
また、仕入れや外注など変動費が発生する事業の場合は、それについても詳細に検討すべきです。
金融機関や公庫も応援したくて融資をしてくれますが、慈善事業ではないので、貸し倒れのリスクは限りなく「ゼロ」に近づけたいのです。
補足資料の重要性
では、これらだけに気を付けて創業計画書を作成すれば十分でしょうか。
答えは「ノー」です。
先ほどの公庫の創業計画書を見ていただくとわかるとおり、長くても1つの項目で3行しか欄がないため、金融機関等を納得させる文章を作成することは不可能に近いです。
もちろん、この用紙1枚だけで融資を受けられることもなくはないです。ただ、それはよほど返済財源が多いか、事業実績や経歴が非常に優れているなど、返済が確実に見込まれる場合に限られます。
なので、絶対に融資を受けたいと考えるなら、この計画書に加えて補足資料を添付する必要があります。
創業計画書の記載項目の別紙記載
前述のとおり創業計画書は記載欄が小さいので、その内容を別紙に記載し、詳しく説明します。
ここで説明された内容により、公庫等が事業のイメージをつかみます。
説得力を持たせるため、これまでの実績や略歴、資格、経験など、事実をしっかりと積み上げて記載することが大切です。加えて、軽視しがちですが、自己アピールについても記載しましょう。家族や知人など、もしものときに助けてもらえる環境についても記載できれば安心感が増します。自己資金に計上していないお金(証券口座や貯蓄専用口座の残高)がある場合も記載すると有効です(通帳写しも提供)。
損益に関する計画
ここまでは言葉で説明していましたが、やはり数字でも本気度を見せる必要があります。
損益に関する計画は、以下のような資料を整理すると伝わりやすいです。
- 売上計画・・・月ごとの売上を3年分くらい想定
- 購入備品・・・創業準備のために購入(予定)の備品の一覧
- ※備品は、内容や購入時期によっては自己資金に含めることができます。自己資金が多いほど有利ですので、準備段階から記録しておき、必ずリストアップしましょう。
- 人件費・・・正社員やパートなど従業員を雇用する場合に必要です。損益計画を作成していくと気付くと思いますが、人件費は損益において非常に大きなウエイトを占めますので、作成しながら人員体制の見直しをかけていくことも大切です。
- 月次の損益計画・・・売上計画の売上、売上原価(仕入れ代など)、販売・一般管理費(家賃、広告費などの経費)を記載し、毎月の経常利益を算出します。
- 資金繰り表・・・4の損益計画の数字を使用し、さらに財務収支なども記載することで、毎月のキャッシュの残高が明確になります。この表で残高がマイナスになれば倒産です。それを防ぐには「いつ、いくら」借入すればいいか、この表で簡単にシミュレーションできます。
- ※資金繰り表は、融資のためだけに作成するのではなく、創業後も常に作成・メンテナンスを続けましょう。これがあれば、資金の状況をきっちり把握できるので、気付かないうちに資金がショートするのを防ぎ、早めの借入など対策をすることが可能です。
- 損益予定表・・・5の資金繰り表から収支を計算し、キャッシュを確保する計画を立てたうえで、融資の返済について整理します。
この中でも5の資金繰り表は、特に重要です。
融資のためだけに作成するのではなく、創業後も常に作成・メンテナンスを続けることで、資金の状況をきっちり把握できます。気付かないうちに資金がショートするのを防ぎ、早めの借入など対策をすることが可能です。せっかく事業が好調なのに倒産する「黒字倒産」も非常に多いです。絶対に避けましょう。
まとめ
創業計画書は、「創業融資」の本気度を示す重要な資料です。特に資金繰り表などは融資の際だけではなく、その後の経営においても参考にできますので、気合を入れて作成しましょう。
とは言え、事業のことを考えながら自分一人で創業計画書に時間をかけられない方も多いと思いますので、悩んでいるくらいなら遠慮せず専門家に相談することが近道になるかもしれません。ぜひ当事務所の無料相談もご活用ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。